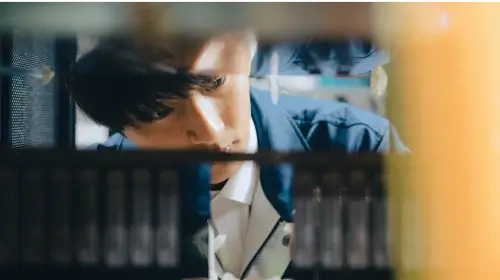プロジェクトストーリー / Project Story 01
「三河おじさん図鑑」
Career 未来を創るキャリア

「おじさん」を軸に、
番組の枠組みを超えたプロジェクトへ。
三河地方に暮らす「おじさん」たちの魅力を伝えるドキュメントバラエティー「三河おじさん図鑑」。その誕生のきっかけは、20代スタッフの「おじさんって、実は面白いかも」というひと言でした。「地域に暮らす“人”の魅力にこそ可能性がある」という想いのもと、今も試行錯誤し続ける制作の舞台裏をご紹介します。
-
- U.M.
- お客様満足創造本部
感動メディア1課 - キャリア入社

-
- Y.S.
- お客様満足創造本部
感動メディア1課 - 新卒入社


はじまりは、「おじさんって面白いかも」の一言。

U.M.
「地域の人が主役の番組を作りたい」と言い始めたのはYさんだったよね。「どんな人にフォーカスすると地域の魅力が伝わるか」を話し合っているときに、Yさんが「おじさん世代って面白いかも」とつぶやいたのがきっかけで、「おじさん世代」にフォーカスすることになりました。

Y.S.
はい。これまでの取材で出会った方々の中に、日本の貝の約6000種中5900種を収集している「貝コレクターおじさん」など、とても魅力的なおじさんたちがいたので、他にもたくさんいるんじゃないかなと。

U.M.
個人的にも、「地域に暮らす“人”の魅力にこそ可能性があるのでは?」と感じていました。私たちの発信ではないのですが、西尾市の団子屋のおばあちゃんがSNSを中心に大きく話題を集めた出来事があったんです。私たちも日々の取材を通して地域の人々の魅力をよく知っているつもりなので、それを発信し、番組を超えた広がりを生み出したいと考えました。


Y.S.
具体的な企画の方向性を模索しているときに見つけたのが、福島県二本松市の岩代観光協会が制作している観光冊子「岩代おじさん図鑑」でした。地域のおじさんたちの魅力を丁寧に紹介されていて、全国的にも話題になっていたんです。

U.M.
私たちが目指していたコンセプトとも一致していましたね。実際に福島の岩代観光協会を訪問して図鑑に登場されている「おじさん」にもお会いしたのですが、「No.16の山崎です」と図鑑No.で自己紹介されていて、この図鑑がご本人たちの誇りになっているんだなと感じました。番組を超えた広がりを目指すなら、自分たちもそう感じてもらえるような企画にしなければと考えました。

Y.S.
岩代では実際におじさんたちに会えるファンミーティングのようなイベントも開催されていますよね。岩代観光協会からは「三河おじさん図鑑」を公認いただいてパートナーシップを築けたのはもちろん、「周囲をどう巻き込んでいくか」を考えるきっかけをいただきました。


企画から取材、SNS運用まで。
20代中心のチームで挑む番組作り。

U.M.
番組を制作するうえで大切にしているのは、最初におじさん世代の面白さに着目した20代のYさんの視点です。おじさん世代がおじさん世代を紹介すると、同じ属性なのでどこか近視眼的になってしまう。そうではなく、いわゆるZ世代の視点、さらに言えば日々地域の人たちを取材しているYさんだからこそ見えてくるおじさんたちの魅力を発信していけば、より広い世代の人たちに伝わるんじゃないかと考えています。

Y.S.
そうしたUさんの意図もあって、番組制作スタッフは、プロデューサーの私だけでなく、パートナーである制作プロダクションのディレクター陣も20代のメンバーで構成されています。今回の番組立ち上げにあたっては、番組内容や制作体制、会社への企画提案など、いずれも初めてだったので、Uさんに教わりながら進めていきました。現在は、取材者の選定やVTR構成の立案、取材、スタジオ出演、さらにはSNSでの宣伝活動など、番組に関する業務を行っています。

U.M.
周囲への説明で苦労したのは「なぜおじさんなのか?」の言語化です。

Y.S.
面白いと感じた私たちの感覚をどう伝えればいいか、表現に悩みましたよね。


U.M.
三河地方は製造業が盛んなエリアなので、それに関わるおじさんも多いんです。「人の魅力を、地域の魅力へとつなげる」というコンセプトを踏まえると、ものづくりに関わっている人が多い属性というのはポイントでした。もちろん、年代的にも人生経験や奥深いストーリーを持っている人が多いというのもあります。

Y.S.
言語化できたおかげで、ニッチなテーマでしたが、社内からも「面白そう」と企画への期待の声が上がってきましたよね。まだ番組がスタートして数カ月ですが、地域の方からは番組の感想だけでなく、「こんなおじさんがいるよ」といった推薦もいただくことが増えてきました。

U.M.
地域の人の魅力をどう伝えていくかはまだ手探りだけど、少しずつ反応も増えてきているよね。

Y.S.
取材でどれだけ魅力を引き出せるかは、今も試行錯誤しています。視聴者に「愛すべきおじさんだ」「会ってみたい!」と思ってもらうには、どれだけおじさんの面白さ、かわいらしさ、素の姿を撮影できるかがバラエティ番組としてのポイントだと感じています。そのためにも、事前の打ち合わせでできるだけ距離感を縮めて、その人の魅力となるポイントを最大限に引き出せるように心がけています。


いずれは「おじフェス」も?
地域の魅力を、番組の外へも。

U.M.
徐々に反響が増えてきましたが、当初描いていた「番組を超えた広がり」という理想まではまだまだ先です。番組を超えた展開としては、たとえば「『三河おじさん図鑑』のおじさんに会うとおじさん図鑑シールをもらえる」など、「おじさんに会いに行きたい」と思ってもらえる仕組みを作りたいと思っています。

Y.S.
私は、最終的なゴールとしては「おじフェス」をやりたいという想いがあります。これまで「三河おじさん図鑑」に登場いただいたおじさんたちには、お店を営む方も多いですし、いろんなおじさんをギュッと集めて地域内外の人に楽しんでもらえるような取り組みを考えていきたいです。

U.M.
そのためにも、まずは番組を盛り上げていかないとね。これまでも地域の魅力を伝えてきたつもりですけど、番組の枠組みを超えて広げていくというのは自分たちにとっても初めての挑戦なので、本当に何がいいのかを試行錯誤している最中です。大きく広がれば、番組への注目度や期待もさらに高まっていると思うので。

Y.S.
番組制作5年目で、番組の立ち上げをゼロからまかせてもらえたことはとても大きな経験になりました。特に、先回りして話題性の高い企画を考え、プロデュースしていく重要性を学べたと思います。プロデュース力はまだまだこれからですが、番組のファンが増えるようにこれからも取り組んでいきたいです。

U.M.
今回のプロジェクトは、Yさんの何気ない一言からスタートしましたが、そこに可能性を感じて、調べ、動き、仲間をつくって、いま番組というひとつの形になりました。正解がないことに挑戦するのは大変ですが、その分、自分のアイデアや行動が誰かの心を動かし、地域に広がっていくことを実感できるのは、この仕事ならではのやりがいだと思います。
Next
「EDFAリプレイス」
約18万世帯のテレビ放送を支える、
設備リプレイスプロジェクト。