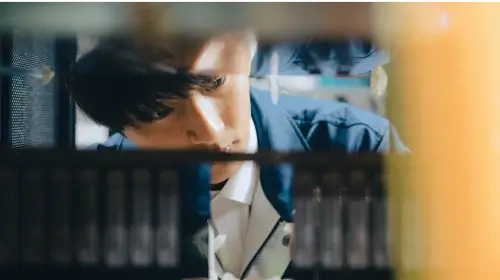プロジェクトストーリー / Project Story 02
「EDFAリプレイス」
Career 未来を創るキャリア

約18万世帯のテレビ放送を支える、
設備リプレイスプロジェクト。
約18万世帯が視聴するキャッチネットワークのテレビ放送サービスは、本社のヘッドエンドから各地域のサブセンターを経由して各家庭に届けられます。から3年かけて、この12拠点に設置された「放送用光増幅器(EDFA)」の全面リプレイスプロジェクトが進行しました。リーダーを務めたのは、配属4年目の若手社員。伴走した先輩社員とともに、挑戦の舞台裏を振り返ってもらいました。
-
- H.T.
- ICTデザイン本部
インフラデザイン課 - 新卒入社

-
- K.Y.
- ICTデザイン本部
インフラデザイン課 - 新卒入社


冗長性の確保で、放送サービスの安定性を高める。

H.T.
キャッチのテレビ放送は、ヘッドエンドと呼ばれる本社内の設備から、各地域にあるサブセンターを経由して、それぞれのご家庭まで信号が届けられます。今回のリプレイスプロジェクトは、ヘッドエンドを含め12拠点にあるEDFAという機器を更改するために行われました。

K.Y.
放送信号は、ケーブルを介して拠点間を伝わりますが、距離が長くなると信号は弱くなっていきます。そこでEDFAによって光を増幅してやる必要があるんです。このEDFAが、FTTH※サービスの開始時に設置されてから10年近く経っていたので、経年劣化によるトラブルを未然に防ぎ、冗長性を確保するためにも新しい機器に入れ替える必要があったんです。

H.T.
冗長性の確保については、機器を2台用意することで、一方が故障してももう一方に即座に切り替えられる構成を採用しました。従来の構成だと、一部の拠点では万一のときに駆けつけて対応するまでの間、放送サービスが止まってしまう状態でしたが、今回の更改でサービス停止時間を1秒未満に抑えることが可能となります。
FTTH:キャッチからお客さま宅までの伝送路すべてを光ファイバーケーブルで構成したネットワークのことをいいます。


K.Y.
こうした大がかりな設備更改プロジェクトは、毎年のように行うものではありません。実際に自分で考えて設計や設定、工程管理などを行っていく経験は、若手の成長にとっても非常に貴重だと考えています。Hさんもまだインフラデザイン課に配属されて4年目でしたが、良いタイミングだったので、彼を中心に進めていってもらおうとリーダーをお願いしました。

H.T.
今回のEDFAにしても、今後10年は更改の予定はありませんからね。

K.Y.
もちろん、Hさんの実力あっての任命です。自分で物事を考えながら、周囲とのコミュニケーションをとって進めていける人なので、まかせても問題ないと考えたんです。基本的には大きな工程管理や調整はHさんが行い、私は実施内容や作業手順の精査を含めた全体的なフォローを行いました。また、現場作業の立ち会いは、他のメンバーも分担して協力しました。


海底ケーブル接続時の光レベル調整など、
多様な課題を経験。

H.T.
更改にあたっては、「性能を担保しながらコストをできるだけ抑える」という観点から新しいEDFAを決定しました。既存機器とは異なるメーカーを選択したこともあって、機器構成を一から再設計する必要がありました。

K.Y.
保守性の観点から、各機器のメーカーは統一するようにしているんです。

H.T.
既存機器の構成の把握、新しい機器の仕様の理解など、どれも初めてのことばかりだったので、自分で勉強しながら先輩にアドバイスを仰ぎ、設計していきました。

K.Y.
特に佐久島は苦労したよね。離島なので、海底ケーブルの利用にあたってさまざまな手続きが必要でしたし、ケーブル接続部分でどうしても光レベルが落ちてしまうので、さまざまな観点からの確認が必要でした。


H.T.
佐久島ではKさんにかなり助けていただきました。特に光レベルがどれだけ落ちるかの計算や、不足するレベルのフォローなど、「これってどうしたらいいんだろう」というポイントが多かったですね。

K.Y.
実際の工事にあたっては、施工を担うパートナー会社との密な調整も必要になったよね。

H.T.
はい。自分は工事を監督する立場だったのですが、細かい意識合わせは慎重に行いました。設計した当人である自分は構成を細かく把握していますが、作業する方はそうではありません。資料にも細かいところを一からわかるように書いて、必ず対面で説明するようにしました。

K.Y.
パートナー会社の方とは、何度も調整を図ってくれていたよね。無事故で終えられるように、手順確認をしっかりやっているのを見ていたので、安心してまかせられました。


切替作業を無事に完遂。
責任ある仕事を経て、
着実に成長へ。

H.T.
切替作業は、放送サービスへの影響を最小限に抑えるため、夜間に実施しました。サブセンターなど、基本的に屋内での作業だったので、夜間でも特に支障はありませんでした。ただ、機器を交換した後に、すべてのお客さまのご家庭で正しくテレビが映っているのかどうかは、確認する手立てがありません。だからこそ、一つひとつの作業内容を作業者の方にしっかり説明して、声かけ・確認は時間をかけて徹底して行いました。

K.Y.
朝になって一部の地域のお客さまから問い合わせがあって、初めてわかるということもあり得ますからね。

H.T.
自分が一から設計をまかされたものが、実際に動いているのを見たときは、とても感慨深かったです。特に佐久島では、他のサブセンターで培った知識を生かしてゼロから設計を考えたので、とても貴重な経験になりました。冗長性を確保できて実際にサービスもより良いものになったので、達成感を感じました。我ながら、がんばったなと思います。

K.Y.
本当に、あらゆる場面で自主的に動いてくれていたので、まかせて良かったと感じています。

H.T.
先輩の指導のおかげです。勤続年数が浅くても、責任ある仕事をまかせてもらえるのは「キャッチならでは」と感じました。

K.Y.
特に技術系の部署では、少数精鋭ということもあって、一人ひとりのスキルを伸ばすために大きな案件を積極的にやってもらっているところがあるかもしれないね。

H.T.
「一回やってみよう」というのはありますよね。実際自分でやってみないとわからないことは多いですから。個人的にも、難しい課題でも、着実に知識を身につけて粘り強く取り組めば、課題を達成できるという自信がつきました。

K.Y.
専門知識はもちろん、自分自身で先々のことを考えて行動することも身についたんじゃないかな。自ら考えられる人、新しい技術に好奇心をもてる人が、活躍できる会社だと思います。
Next
ライフとワークの変化でたどるタイムライン
受賞・異動・出産を経た、
これからの働き方。